
TALK
クロストーク
止めない仕組みを支える、
インフラの現場。
社会や企業の“当たり前”を支える──それがAWS ITインフラ部門の使命です。
サーバーやネットワークなど、止められない仕組みを扱う現場では、綿密な準備とチームでの協力が欠かせません。
今回は、先輩と後輩が語る「責任とやりがい」、そしてAWSだからこそ挑める“インフラの最前線”をお届けします。

TALK
MEMBER
トークメンバー
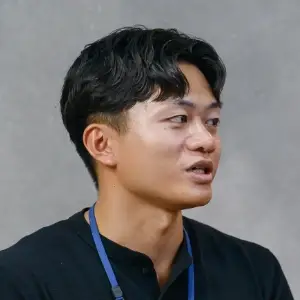
長谷さん
ソーシャル
ソリューション部
ITインフラ
2023年度入社

俵本さん
ソーシャル
ソリューション部
ITインフラ
2016年度入社
入社のきっかけとITインフラの魅力
俵本:
就活していた時は、正直なところ「ITインフラ」という分野をよく知らず、開発やプログラマーといった職種を中心に探していました。
いくつかの企業を受ける中で、AWSは特に若手の声に耳を傾けてくれる雰囲気を強く感じました。
面接の場でもこちらの思いをしっかりと受け止めてくれて、若手でも挑戦できる環境があるのではと感じたことが、入社の大きな決め手になりました。
長谷:
私は当時、ITはあらゆる分野で必要不可欠になってきており、幅広い課題を解決できる分野だという点に大きな魅力を感じていました。
最初は開発やプログラマーの仕事を想像していましたが、入社後の研修で各部署の管理職の方から直接お話を伺う機会があり、そこで初めてITインフラの具体的な役割を理解しました。
お客様の会社に足を運び、環境を構築し、直接ニーズに応えるという点に、他にはない魅力を感じました。
俵本:
ITインフラは水道や電気と同じように「当たり前に動いている」ことが求められます。
だからこそ、社会や企業の基盤を支える重要な仕事であると実感しています。 AWSの一員としてこの責任を担えることに、やりがいと誇りを持っています。
長谷:
例えばお客様先で大きな課題が発生した際、それを部署の先輩方と協力して解決できたときには、お客様の業務を支えられたという達成感を強く感じます。
こうした経験を積み重ねられるのも、風通しが良く挑戦を後押ししてくれる会社だからこそだと感じています。

初めての現場で印象に残ったこと
長谷:
最初の出張はもちろん上司と一緒に行ったんですけど、そのとき「準備って99%なんだな」って実感しましたね。当時は上司がいたから、分からないことや予想外のこともフォローしてもらえましたけど、自分ひとりでお客様先に行っていたら絶対に解決できなかったと思います。
やっぱり現地作業も大事なんですが、それを円滑に進めるためには事前の準備が一番重要で。「現地では準備したことを実行するだけ」という状態を作っておくことが必要なんだなと感じました。
準備不足のまま現地に行くと、自分の焦りや態度がそのままお客様の不安につながってしまう。だからこそ、お客様に安心していただけるように、自信を持って作業できる準備が欠かせないなと思います。
俵本: 確かに。トラブルって、もともと意識してなかったところから起こることが多いですもんね。だから事前準備って、ただ段取りを整えるだけじゃなくて、「こうなったらこうなる」という影響まで踏まえて考えておくことが大事だと思います。
長谷: 確かにそうですね。
俵本:
僕自身は、お客様の本番環境を触るのが今でも怖いんですよ。初めてのときだけじゃなくて、今でも「壊したらどうしよう」「電気止めたら大変だな」とか、常に緊張感があります。
その恐怖をなくすためにも、事前の準備や「最悪の場合はこうやって元に戻す」というリカバリ方法まで考えておく。それがあるからこそ安心して取り組めるし、うまくいったときの達成感も大きいですね。

チームで乗り越えた経験
俵本:
そういう意味で言うと、やっぱりITインフラってサーバーやネットワークがありますけど、人によって得意分野が分かれますよね。
でもインフラって両方が密接に繋がっているから、トータルで導入支援をしていく必要がある。
その中で、ネットワークが得意な人に聞いたり、サーバーが得意な人に聞いたりする。案件に直接アサインされているかどうかに関わらず、最終的にはみんなで完成させていく──毎回そんな形になっていると思います。
長谷:
そうですね。俵本さんがおっしゃったように、サーバーとネットワークが繋がっているからこそ、それぞれ得意な人とコミュニケーションを取りながら解決していくのが部署の特色だと思います。
お客様の環境で「なぜこの設定になっているんだろう」とか「これはお客様の要望でこうしているんだっけ」と考えるときに、詳しい人に相談しながら問題解決を進めていく。
そうすることで達成感がありますし、次に同じような問題が起きたときには自分の力で解決できるようになる。
さらに、その経験を他のメンバーに共有できることにも繋がるんだと思います。
俵本: そうですね。個々のノウハウを共有していけば、その人自身がやったことのないことでも、チームとして経験があれば対応できるようになる。そこがチームでやる強みですよね。

これからチャレンジしたいこと
俵本:
部署としては、まだまだ物理機器を扱う案件が多いんですよね。だから今後はもっとクラウドやSaaSにも対応できるようにしていきたいですし、それに限らず全体的に提案力や技術力を高めていきたいと思っています。
自分だけじゃなく、メンバーにも積極的に挑戦してもらいたいですし、管理職という立場上、学べる環境づくりを整えていきたいと考えています。
長谷:
自分はまず、製品に関するノウハウや知識の幅を広げたいと思っています。案件で扱う機器や製品の設定をノウハウとして蓄積しておけば、後輩がその製品に対応するときの助けになりますし、自分自身も急な保守や依頼に柔軟に対応できるようになる。
今は設計を中心に担当していますが、今後は営業にも関わって、ただ設計するだけでなく付加価値を持たせて最適解を提案できるようになりたいと思っています。
俵本:
例えばバックアップ製品であれば、その製品固有の操作だけじゃなくて、「バックアップとはどういう仕組みか」という知識を身につけておくと、別の製品にも応用できるんです。
ネットワークも同じで、CiscoやPalo Alto、NetAppなどメーカーは違っても基本の仕組みは変わらない。だから仕組みを押さえておけば幅広く対応できると思います。
長谷:
確かに…。ありがとうございます。
製品ごとにひたすら覚えるよりも、仕組みとしてノウハウを蓄積する。そうすれば新しい製品に触れるときや後輩に教えるときに説得力が増しますし、理解のスピードも違ってくると思います。
俵本: そうですね。各メーカーごとの細かい設定に違いはあっても、やっていること自体はほとんど一緒ですから。仕組みを理解していれば、吸収も早くなるんじゃないかと思います。
未来の仲間へのメッセージ
長谷: 僕としては、やっぱりこの部署はお客さんと関わることが多いので、元気で活気があって、コミュニケーションが好きな人がすごく向いていると思いますね。そんな仲間を迎えたいと思っています。
俵本:
自分は、さっきの話にも通じるんですけど、ITインフラの仕事って「この設定がこうだからこう動く」という論理的な思考が求められるんですよね。
だから、日常生活でも「これ何でだろう?」と気になったら調べずにはいられないタイプの人は、この仕事にすごく向いているんじゃないかなと思います。

TALK



